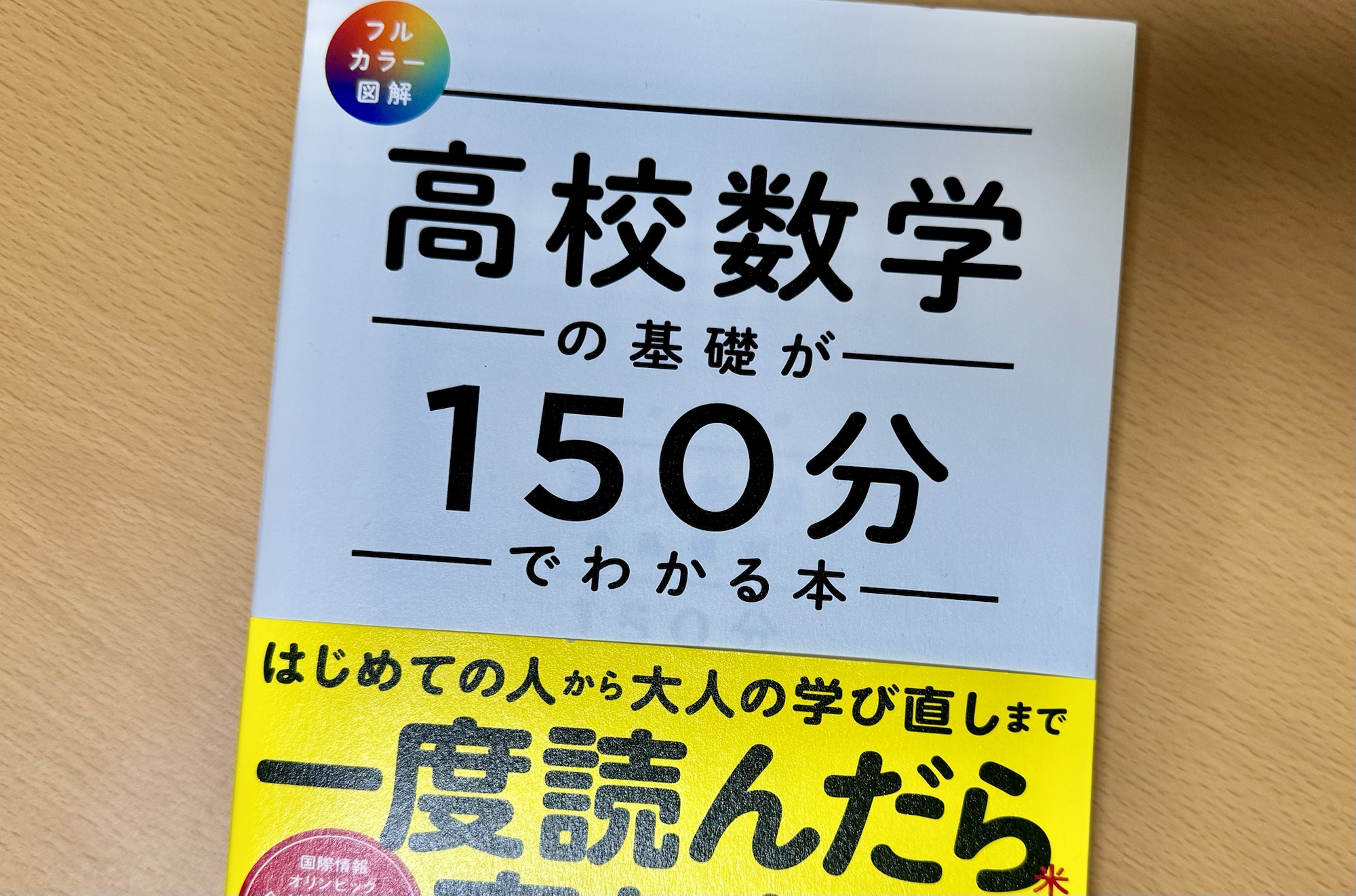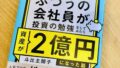「自分が何をわかっていないのか、わからない」。
この感覚に心当たりのある人は多いと思う。私もその一人だった。特に高校数学のような抽象的な分野では、ある項目の理解ができていないと「理解の壁」が突然立ちはだかり、目の前の数式やグラフがまるでわからなくなる。
そんな中で出会ったのが、米田優峻さんの『高校数学の基礎が150分でわかる本』だ。本書は、単なる“やり直し数学”ではない。もっと根本的な、「考え方」そのものを見直す機会をくれる本だった。
「数学の世界に入れなかった自分」が変わり始める
私は学生時代、数学の教科書を開くたびに「で、これは何の役に立つの?」と思っていた。確率や関数、ベクトル…。どれも「そういうもの」として習うだけで、なぜそれが必要なのか、どうしてそう考えるのかは説明されない。
ところがこの本では、その「なぜ?」に真っ向から向き合っている。例えば「関数とは何か」という問いに対して、ただ公式を示すのではなく、「変化を見るための道具」「現実を数で捉えるレンズ」として説明されている。私はこの時、「ああ、そういう風に世界を見るのか」と、数学の見え方が変わった。
さらに面白いのは、読み進めるうちに、自分の頭の中で「概念の地図」ができてくることだ。点と点が線でつながり、バラバラだった知識が意味を持ち始める。それはまるで、モザイクがゆっくりと鮮明な絵になっていくような感覚だ。
抽象概念の「考え方」まで解像度が上がる
特に感銘を受けたのは、抽象的な概念へのアプローチだ。たとえば集合や命題といった“空中戦”になりがちなテーマでも、この本では視覚的な図と具体的な例を使って、「概念」そのものに触れさせてくれる。
たとえば「命題」は、「論理記号の暗号文」のように感じがちだが、この本では「もし上司が出張なら、私は定時に帰れる」といった実生活の中での“論理”から説明が始まる。数学的思考が、いきなり空から降ってくるのではなく、日常の延長線上にあると感じられた。
「高校の数学をわかりやすい例で説明してくれています。例に部長、副部長などの会社チックな例えや投資の話など、社会人に身近な言い回しが出てくるのが嬉しい」
このような声に共感する読者は少なくないだろう。抽象に弱い人間にとって、「具体」から始まる解説は、それだけで救いになる。
「わからないことを掘り下げる」力をくれた
この本を読み終えた後、私は一つの習慣を持つようになった。それは、何かを理解できなかったときに、「なぜわからないのか」を言葉にしてみること。
たとえば、数列の漸化式がわからない時、「式が難しいから」ではなく、「この式が何を表しているのか、意味がイメージできない」と分解してみる。その“わからなさ”にラベルを貼ると、GPTや書籍などを使って自力で調べることができる。
こうして、「わからない」状態がただの壁ではなく、“探求の入口”に変わった。この感覚の変化は、勉強法そのものの転換だったと言える。
レビューから見る、本書のリアルな魅力
Amazonや楽天ブックスのレビューでも、本書に対する共感の声が数多く寄せられている。以下、印象的だったものを紹介したい。
| レビュー内容 | 共感した点 |
|---|---|
| 「数学挫折したまま社会に出て後悔してる者です。概念理解を促す例えが秀逸で、図が適格」 | 私もまさに“数学挫折組”だったので、深く共感 |
| 「学生の頃の教科書がこれだったら、数学もっとできるようになっていたと思います」 | 数学嫌いだった過去の自分に贈りたい一冊だと感じた |
| 「難しい数式ではなく、発想の転換で数学の世界に入れるのが新鮮」 | 公式ではなく“考え方”を教えてくれる構成に共感 |
数学は、誰にでも開かれた「思考の技術」だった
読み終えた後、私が一番強く感じたのは、「数学は、思考のための道具なのだ」ということ。計算が速いとか、答えが合うとかではなく、「どうやって問題に向き合い、どうやって整理するか」。それこそが、数学が私たちに教えてくれる力だ。
たとえば、感情的に話がすれ違う場面や、情報がごちゃごちゃしているとき、冷静に「前提は何か」「関係はどうか」と整理する力は、数学的思考そのものだ。
そしてその入口を、この本はわかりやすく、やさしく開いてくれる。まるで、長年閉ざされていた扉が、そっと開いたような感覚だった。
こんな人に読んでほしい
- 学生時代に数学を嫌いになった人
- 「論理的に考える力」を身につけたい社会人
- 「わからないことがわからない」状態を抜け出したい人
- AIやGPTでの学びをより深めたい人
- 勉強への苦手意識を、少しでも克服したいすべての人
これは数学の“リスタートボタン”だ
『高校数学の基礎が150分でわかる本』は、過去に数学に挫折した人にこそ手に取ってほしい一冊だ。「数学なんてもう無理」と思っていた自分でも、「もしかしたらわかるかも」と思わせてくれる力がある。
これは、学びを取り戻す“リスタートボタン”のような本だ。そしてそのボタンを押した瞬間から、知ること・考えることが少しだけ楽しくなる。