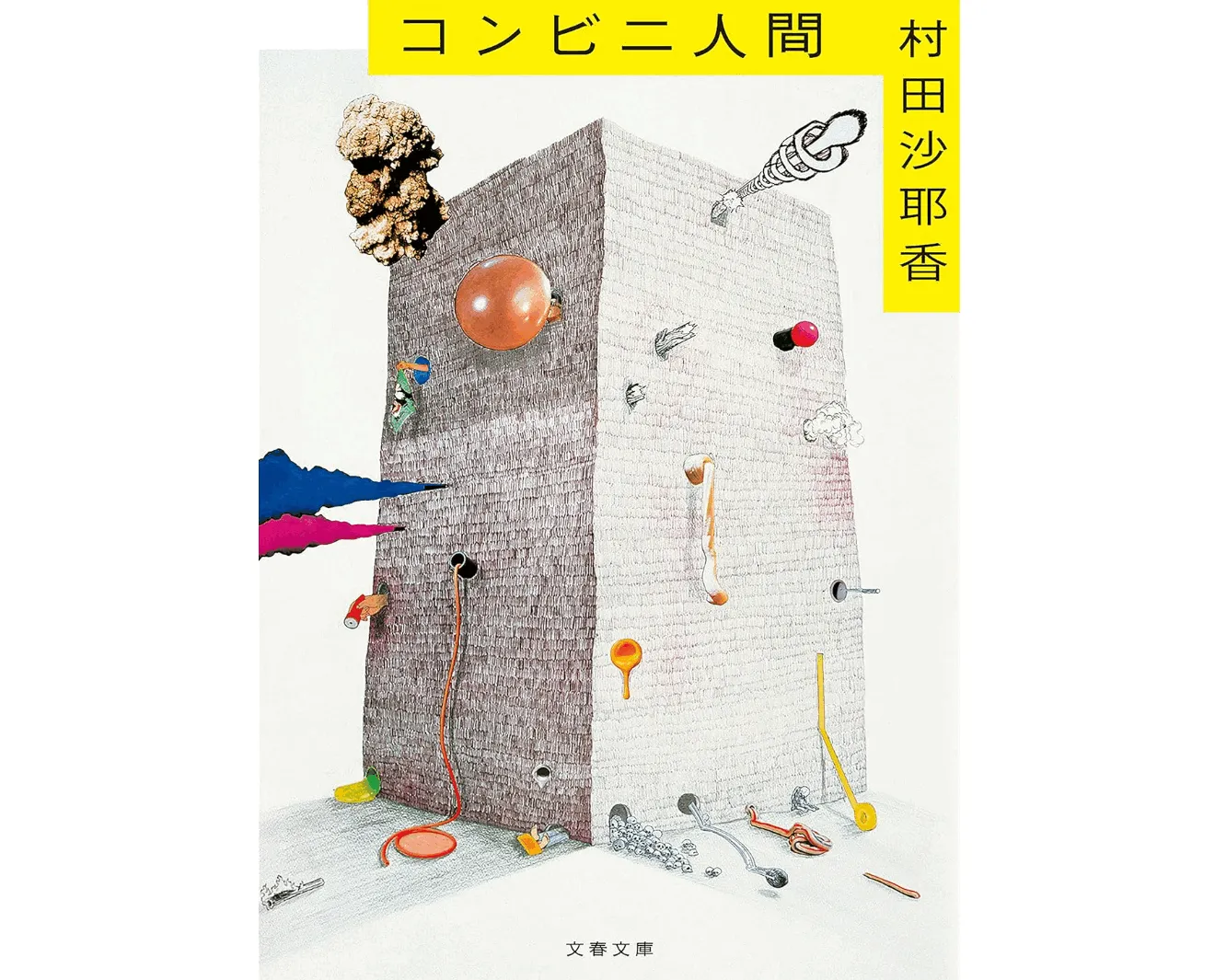村田沙耶香の小説『コンビニ人間』を読んだ。最初の印象は、「なんて変な人なんだろう」というものだった。主人公・古倉恵子は、感情や人付き合いの機微を持たない。けれど、その異質さが、読み進めるうちに「異様にまっすぐな感性」に見えてくるから不思議だ。
世の中の多くの人が「こうあるべき」に縛られて生きているのに、彼女はそれを「模倣することでしか理解できない」という出発点から始まっている。
これは一見するとズレているようで、でもどこか潔くもある。「私は社会に適応しているフリをしている」という自覚と、「本当の自分なんてそもそも持っていない」という開き直りが、私たちの中にも実は潜んでいる気がして、ザワザワするような共感を覚えた。
コンビニという「擬似社会」の中で
印象的だったのは、古倉が働くコンビニを「世界の縮図」として捉えていることだ。毎日決まった時間に出勤し、マニュアル通りの笑顔と挨拶を交わす。ここには確かに人間関係があるのだが、それはあくまで「記号としての人間関係」だ。深くつながることもなく、しかし誰もが役割を果たしていれば成り立つ。
この関係性が、現代の職場やSNSとどこか似ていると感じた。本音よりもコードやルールに沿うことが求められる現代社会の、ある種の風刺だとも言える。
白羽との奇妙な同居生活
物語後半、古倉と白羽という社会不適合者同士の同居生活が始まる。このパートには、まるで現代の「世間体」という名の亡霊がリアルに描かれていた。結婚していないと怪しまれ、正社員でないと責められる。そんな空気の中で、「形式だけ整えれば、社会の目を欺ける」という諦めと打算が、じわじわと沁みてくる。
笑ってしまうほど不器用な二人のやりとりに、人間関係の形式性が際立つ。本当の幸せって、どこにあるんだろう?と考えさせられた。
豆知識: 村田沙耶香さんは実際に18年間コンビニで働きながら執筆を続けていたという事実がある。あの「コンビニの描写のリアルさ」は、まさに作家自身の観察眼と経験に基づいていた。

「普通」の正体とは?
結局のところ、古倉の異質さは、私たちが普段当たり前だと思っている価値観を逆照射してくれるものだった。結婚や就職、会話の空気を読むこと、愛想笑い。すべてが「正解」として刷り込まれている社会で、本当にそれが自分の価値観なのか、とふと我に返る瞬間がある。
古倉は、社会のマニュアルをなぞりながらも、最後に自分の違和感に正直になる。その決断は、風変わりなようでいて、ものすごく真っ当な生き方にも思える。「コンビニ店員」という型に自分を当てはめて安心していた彼女が、物語の終盤でその型すら手放す場面には、清々しささえあった。
異質は、もしかして「本質」なのかもしれない
『コンビニ人間』は、異質な人物を描きながら、私たちがどれほど「普通」を演じているかを問う作品だった。読み終えてから、どこか気恥ずかしい気持ちになったのは、自分の中の模倣癖を突かれたからかもしれない。
笑えるようで痛烈、奇妙なようで深く共感できる一冊だった。もし「生きづらい」と感じているなら、古倉の視点に一度身を置いてみると、見える景色が少し変わるかもしれない。