2025年8月18日、JPYC株式会社(代表取締役社長:岡部典孝)は、資金決済法第37条に基づく「資金移動業者」の登録(関東財務局長 第00099号)を取得したと発表しました。
これにより、JPYCは「日本円と1:1で連動するステーブルコインを発行できる、国内初の資金移動業者」となりました。
JPYCは「日本政府公認」ではありませんが、同時に日本の法律に準拠して発行される可能性が高い国内円ステーブルコインの一角です。
暗号資産が公式的な金融資産になっていく動きは続いています。

JPYC誤解を整理
| 項目 | 現状 | 補足 |
|---|---|---|
| 日本政府の公認か | ❌ 国が認可しているわけではない | そもそも政府が特定の通貨を公認する制度はない |
| 日本の法律に従って発行されるか | ⭕ 新JPYCは改正資金決済法の枠組みで出てくる予定 | 「電子決済手段」としての合法ステーブルの制度枠組みあり。 |
| 金融庁に管轄されるか | ⭕ 発行者が登録制を取得 | 発行会社は資金移動業者の登録を取得。 |
| 使い道があるか | △ これからという段階 | 国内Web3決済・トークン証券・RWA(Real-World Assets)の基盤候補として挙がっている。 |
実際の立ち位置はこう
JPYCは、政府が推す通貨でも民間の怪しい実験トークンでもなく、日本法に合わせて動く国内合法ステーブル陣営の一つで、「公認」という言葉を使うとミスリードになりますが、次のような要素が揃ってきています。
- 法制度の整備にあわせて動いている。
- 発行会社が登録制を取得している。
- 円と1:1を目指しているという公表あり。
したがって、現状では国内で最も「表に出やすい」円ステーブルコインの実用候補と言って差し支えないでしょう。
「何となく使い道が見えない」という印象
実際には、JPYCはまだ爆速で使われているという段階にはありません。
しかし、背景の潮流を見れば「将来必要になるテーマ」であることも十分うなずけます。
追い風になっている事実
以下のような動きが、円のデジタル化・円建てステーブルコイン普及を後押ししています:
- 日本国内で不動産や国債・未公開株のトークン証券化(ST/RWA)への関心が急増している。
- 大手銀行・金融機関(例:三菱UFJ、みずほ、SMBC、野村など)がWeb3金融に参入し始めている。
- 海外ではUSD建てステーブル(例:USDCなど)で運用・送金が進んでおり、日本だけ円のデジタルが無いという状況が「致命傷になりうる」という議論が出ている。
- 法人がオンチェーンで決済・会計処理を行いたい、というニーズが確実に来ている(すでに実証実験が進んでいる)。
つまり、円のデジタル化は避けられない流れであり、そしてそのとき必要になりうるのが円ステーブル(例:JPYC/他)というわけです。
じゃあ今買うべきか?
| 判断 | 結論 |
|---|---|
| 投資目的(値上がり狙い) | ❌ ダメ。ステーブルコインである以上、値上がり益は期待できない |
| 実需・将来準備目的 | △ 少量ならあり(技術・運用を慣れておく意味で) |
| 将来の備えとして | ⭕ Web3版銀行口座のように捉えれば意味がある |
おすすめプラン
現状の向き合い方で最も合理的なのは、
今は大金を投入する必要なし。だが将来のために接続環境だけ用意しておこう。
具体的には、
- ウォレットを作っておく(例:MetaMask、Rabbyなど)
- JPYCをほんの少しだけ(例えば1,000円分)入手して触ってみる(DEXでスワップ等)
- 送金・ガス代・チェーンの仕組みを理解しておく → これは将来円デジタル時代で大きな差がつきます。
この準備をしておくことで、波が来たときに「慌てて勉強を始める」ではなく「既に基礎がある」という状態を作れます。
JPYCはどうなるのか
JPYCは「日本政府の正式な発行通貨」ではありません。しかし、法律に準拠し登録制を取得しており、円ステーブルコインとしての実用候補の一つです。
値上がりを狙った投資対象としては意味が薄く、実務利用・将来の備えとして少量保有+環境整備というアプローチが現実的です。
今は100%対応の段階ではありませんが、2030年~2040年代に向けて円デジタル時代の入口に立っているという意味では、「今から準備しておくメリット」は特にありませんでした。

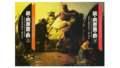

コメント