ChatGPTが公開されたのは2022年11月。わずか3年後の2025年7月には、世界で週7億人以上が使い、1日25億件以上のメッセージがやりとりされるまでに成長しました。
1秒間におよそ29,000件もの対話が行われている計算で、これはSNSやスマートフォンの普及をはるかに超えるスピードです。最新のNBERワーキングペーパー「How People Use ChatGPT」では、この驚くべき広がりを定量的に分析し、人々が実際にどんな場面で、どんな意図で、どんな目的に使っているのかを明らかにしています。
2025年9月の最新の論文です。

7割は仕事以外の用途:日常のパートナーに
まず注目すべきは、利用の大半が「非仕事用途」であることです。
2024年6月時点では非仕事利用が53%でしたが、2025年6月には73%へと拡大しました。
つまり、ChatGPTは仕事効率化だけではなく、生活や趣味に直結する「日常の相棒」として定着しているのです。
相談(Asking)が最多:ただの代行や雑談ではない
調査では、メッセージを意図別に「Asking(相談)」「Doing(代行)」「Expressing(表現)」に分類しています。その結果、全体の49%がAsking、40%がDoing、11%がExpressingでした。
ここで言う「相談(Asking)」とは、心理的なカウンセリングではなく、より良い判断や意思決定のための相談です。例えば「来月の予算をどう立てるべきか」「健康保険を選ぶときに注意点はなにか」「歴史的にこの出来事の原因は何か」といった、実務的・学習的な質問です。つまりChatGPTは、単なる会話相手やアウトプット代行者ではなく、意思決定を支えるアドバイザーとして機能しているのです。
補足: カウンセリング的な「感情の吐露」は全体のわずか1.9%にすぎません。多くの人がChatGPTを「心理相談ツール」と思い込んでいる印象とは実際には異なり、大半は知識や判断材料を求める利用なのです。
教育やレシピなど生活支援が大きな割合を占める
会話のトピックを分類すると、「Practical Guidance(生活や教育のアドバイス)」「Seeking Information(情報検索)」「Writing(文章作成・編集)」の3つが合計で全体の77%を占めています。
なかでも教育利用は顕著で、全メッセージの10%、Practical Guidanceに限れば36%が「家庭教師・学習支援」として使われています。さらに料理やレシピに関するやり取りも多く、日常生活に直結した「AI家庭教師・AI主婦の知恵袋」として機能しているのです。
検索エンジンの代替としての利用
情報検索(Seeking Information)は24%を占めており、これは従来の検索エンジンの役割を部分的に置き換えていることを意味します。違いは「カスタマイズ性」です。
例えば「ボストンマラソンの年齢別標準タイム」を知るのは検索でも可能ですが、「自分の練習レベルに合ったマラソン練習メニュー」を作らせるのはChatGPTならではです。
検索と相談を融合した「検索の次の形」として、すでに多くの人が移行しています。
生成AIは「修正AI」だった
文章関連の利用(Writing)は24%ですが、そのうち2/3は「既存の文章の修正・要約・翻訳」でした。
ゼロから小説や記事を書かせるよりも、「自分の書いた文章を磨いてもらう」「要点をまとめてもらう」など、既存アウトプットの改善に活用されているのです。
この点は、ChatGPTが「新しいものを創るマシン」ではなく「人間の成果を整えるパートナー」として受け入れられていることを示しています。
男女差の逆転:女性ユーザーが多数派に
リリース初期、利用者の約8割は男性でした。しかし2025年には女性が過半数を占めるまでに逆転しています。
利用傾向も性別で違いがあり、女性は「Writing」「Practical Guidance」を多用し、男性は「Technical Help(技術支援)」「Seeking Information」「Multimedia(画像生成など)」を多用しています。AI利用のジェンダーギャップが短期間で解消されたどころか逆転した事実は、社会の変化を象徴するトピックです。
Z世代は日常に、大人は仕事に
年齢層別では、18〜25歳が全体の46%を占めています。
若者は学習や趣味、雑談など日常的に使う割合が多く、年齢が上がるほど仕事関連の利用比率が増えます。
例外は66歳以上で、仕事関連利用はむしろ少ない傾向が見られました。つまり「Z世代にとってChatGPTは生活必需品」「ミドル世代にとっては業務効率化ツール」という二重の顔を持つのです。
低中所得国での急速な普及
利用の広がりは高所得国だけに限りません。
2024年から2025年にかけて、特にGDP1万〜4万ドル層の国で利用が急増しました。
多くの低中所得国でChatGPTの浸透が進んでおり、これは「デジタル格差を縮める可能性」を示唆しています。高額な教育機会やコンサルティングサービスが得にくい国々で、ChatGPTが代替的役割を果たしている可能性があるのです。
職業ごとに異なる“使いどころ”
職業によって利用傾向が大きく異なる点も明らかになりました。
マネジメントやビジネス系では仕事関連利用の半分以上がWriting(報告書・メール作成)。
コンピュータ関連職では37%がTechnical Help(コードやデバッグ)。教育や医療などの専門職ではWritingとPractical Guidanceが中心。非専門職では生活支援的な利用が目立ちます。職業アイデンティティがChatGPTの使い方に表れているのです。
ユーザー満足度は急上昇
2024年後半の段階では「良い体験は、悪い体験の3倍」でしたが、2025年半ばには「4倍超」に改善しました。
特にAsking(相談系)の満足度は高く、Doing(代行)やExpressing(表現)よりもポジティブな評価を得ています。モデルの改良と同時に、ユーザー自身が「どう聞けば良い答えが返るか」を学習していることも影響していると考えられます。
ChatGPTの本質は「思考補助」
職務内容に基づくONET分類では、仕事利用の8割が「情報収集・整理・解釈」や「意思決定・助言・創造的発想」に関連していました。
つまりChatGPTの強みは、単なるタスク代行よりも「人間の思考を補助すること」にあります。これは「検索より深い相談相手」としての立ち位置を明確に示しています。
ChatGPTは相談できる伴走者
ここまで見てきたように、ChatGPTは「仕事を代わりにするAI」以上に「生活を支える相談相手」として浸透しています。
非仕事利用が増え、教育やレシピ、生活アドバイスが日常に入り込み、ジェンダーや世代を超えて幅広く利用されています。検索エンジンの代替としても機能しながら、心理相談的な利用は少数派。つまり、ChatGPTの本質は「万能ロボット」ではなく「判断や発想を助ける伴走者」なのです。
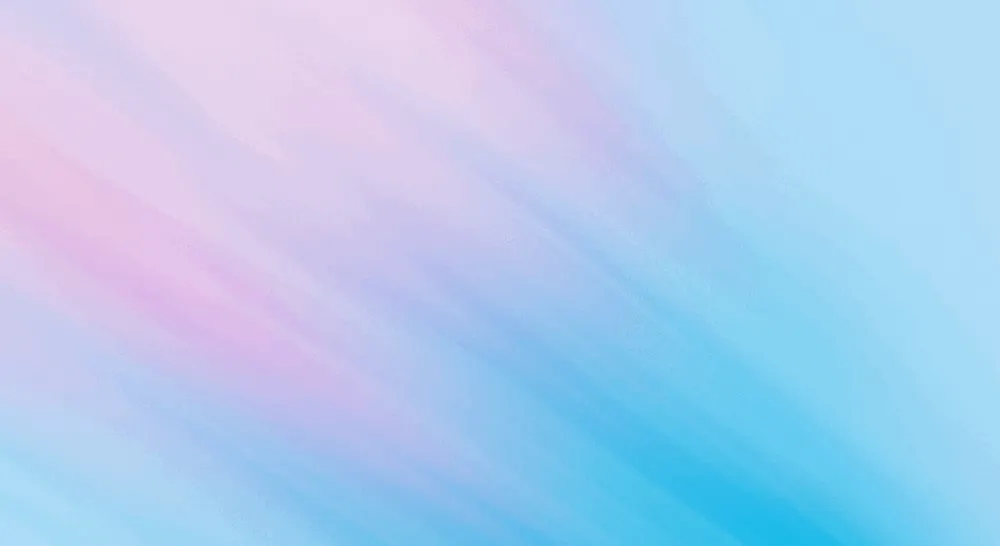


コメント