2025年秋。宮城県知事選では、参政党が事実上支援した候補が現職を猛追し、仙台市では票で上回る結果となりました。これは偶然でも地方特有の現象でもありません。
政治学的に言えば、「ネット民意による地方選ハック」が本格的に始まったということです。次は、あなたの県かもしれません。
では、主婦やサラリーマン、高齢者など、影響力を持たない普通の人はどうすればよいのでしょうか。ここでは、参政党の構造的な強さを分析し、それを上回る具体的な防衛策を示します。
参政党の強みは「情報戦」、民主主義の裏を突く構造
参政党は、単なる保守政党でも陰謀論団体でもありません。彼らの特徴は、感情をアルゴリズム化した政治運動です。たとえば、YouTubeやX(旧Twitter)で「利権」「外国人」「メガソーラー」「国防」といったキーワードを中心に、共感を誘うショート動画を量産します。
これは広告運用の手法とほぼ同じで、ターゲティング広告のロジックを政治に応用したものです。
つまり、参政党は「情報の真偽」ではなく「どの感情を刺激すれば拡散するか」で動いています。論理や政策ではなく、怒り・不安・同調をクリック率に変換する。そこに票が生まれる。
SNS上で強い言葉を繰り返せば、アルゴリズムが勝手に露出を増やしてくれる。この構造が、既存政党がどれだけ真面目に政策を説明しても埋もれてしまう理由です。
豆知識:デジタル政治学では「感情優位型選挙(Affective Campaign)」と呼ばれます。論点よりも感情刺激で投票行動を決める現象で、SNSの普及以降、欧米でも急速に増えています。
「メディア扇動」の歴史、テレビが終わり、ネットが始まっただけ
政治における「扇動」は、SNSで突然生まれたものではありません。むしろ、20世紀のほとんどの時期は、テレビ・ラジオ・新聞といった旧来のマスメディアがその役割を果たしてきました。
戦前・戦中の大本営発表、冷戦期の赤狩り報道、そして平成初期のワイドショーによる社会的制裁。いずれも、「感情を先に動かし、理性を後退させる構造」を利用して大衆を誘導した点で共通しています。
たとえば、戦時中の新聞各紙は「戦果拡大」「連勝」といった見出しを掲げ、国民の不安や疲弊を隠しました。アメリカではラジオが政治扇動の道具となり、ルーズベルト大統領の「炉辺談話」から、ジョセフ・マッカーシーの共産主義狩りまで、聴衆を「正義」の名でまとめ上げました。日本でも、バブル崩壊直後の経済報道や社会事件報道が、冷静な分析よりも恐怖や同調を煽った例が少なくありません。
旧メディア扇動には、ある種の免疫がある
これらのメディア扇動には、ある種の免疫が時間とともに生まれました。テレビで誰かが泣きながら主張しても、視聴者は「演出かもしれない」と一歩引いて見るようになった。新聞の社説を読んでも、「これはこの社の立場だ」と理解する人が増えた。つまり、テレビ・新聞に対しては社会が批判的読解力を身につけたのです。
しかし今、同じことがSNSで起きています。しかも厄介なのは、そこに「編集者」も「検証者」もいないことです。YouTubeの動画、Xのポスト、LINEのオープンチャット。どれもが瞬時に数十万単位で拡散し、誰も責任を取らずに消える。
テレビにかつてあった「自浄作用」も、新聞が持っていた「第三者校閲」も、ネットには存在しません。フェイク動画が事実より早く広まり、デマ投稿が翌日には意見として定着してしまう。参政党が選挙を「ハック」できるのは、まさにこの真偽不明の無法地帯が、まだ市民にとって新しすぎるからです。
SNSを盲信しない、熱狂が加速している
多くの人はまだ、SNSを情報インフラではなく「娯楽」として使っています。だから、政治的発言や陰謀論に出会っても、無意識に「エンタメ」として受け取ってしまう。だが、その軽さこそが、民主主義を壊す最大の脆弱性です。SNSの投稿には放送倫理も編集方針もなく、責任の所在も不明確。誰も止めないし、誰も検証しない。つまり、SNSは無検証の政治放送局が無限に並んでいる状態なのです。
かつて新聞やテレビが誤報を出しても、翌日には訂正記事や謝罪報道がありました。しかしSNSには翌日という概念すらなく、昨日のデマを上書きする今日の熱狂が生まれるだけです。この「時間の無限リセット」が、参政党のような勢力にとって理想的な土壌となっています。選挙ハックとは、情報の洪水の中で正確さより即時性を武器にする行為であり、その武器を使う側にはもはや編集者も監視者もいません。
テレビの時代、扇動は一方向でした。だがSNSの時代、私たち一人ひとりが発信者であり扇動者でもあるという現実を直視しなければなりません。問題は、技術ではなく、リテラシーの成熟速度が社会変化に追いついていないこと。つまり、ネット扇動に対して私たちはまだ初心者なのです。
この未成熟な民主主義空間が、参政党のような感情政治の温床になっています。SNSに「検証者」と「第三者評価」が不在な限り、彼らは事実よりも速度で勝ち続けるでしょう。
いま必要なのは、技術的な規制ではなく、市民一人ひとりが冷静に見る目を取り戻すこと。その力を持たないまま放置すれば、次の選挙も、また同じようにハックされる未来が待っています。
「理性が届かない政治」への対抗法、無関心を武装解除する
参政党の戦略が効く最大の理由は、多数派の沈黙です。中道層や一般層が「政治は難しい」「話すと揉める」として会話を避けた瞬間、政治空間の主導権は声の大きい少数に奪われます。実際、宮城県ではX上での発信の8割以上がオレンジ色のシンボルを掲げる参政党支持者によるものでした。数ではなく、声量の勝利です。
この構造を変える唯一の方法は、「自分は無関心ではない」ことを示すことです。大声で発信しなくても構いません。むしろ、家庭や職場の小さな会話で「私はあの政党には違和感がある」「情報が極端すぎる」と口にするだけでよい。政治的発言がタブーになった社会では、極端な意見ほど支配的になります。無関心は中立ではなく、極端を助長する燃料なのです。
主婦・サラリーマン・高齢者が現実的にできる防衛的市民行動
まず、家庭と職場のミニ・パブリックスフィア(小さな公共圏)を取り戻すことです。
主婦の方であれば、家族やママ友との会話の中で「SNSの情報って本当なのかな」と一言添える。
サラリーマンであれば、昼休みに「最近この政党の動画がよく出てくるけど、どう思う?」と話す。
高齢者であれば、ご近所の集まりで「昔と政治のやり方が違うね」と気軽に話題を出す。どんなに小さくても、こうした対話の積み重ねが扇動政治に対する免疫になります。
さらに有効なのは、地域の信頼ネットワークを使って事実を共有することです。参政党が撒くデマの多くは「利権」「外国人」「陰謀」という単語で作られています。地方紙やNHK、河北新報などがファクトチェック記事を出したら、リンクを家族LINEや自治会掲示板で紹介する。信頼できる情報を非対立的に流すことが、最も有効なカウンターになります。
また、投票行動の前段階として「自分は誰に投票するのか」を明文化しておくことも重要です。紙でもスマホでも構いません。「A候補の経済政策、B候補の福祉政策」と比較してみる。人は書くことで自分の判断を整理します。無意識のままノリで投票することを防げます。
参政党の「選挙ハック」を止める具体策、選挙法の盲点を突く戦略への備え
参政党は、法のスキマを突く巧妙な選挙ハックを多用します。公示前からの動画拡散、候補者との共同ライブ配信、LINEオープンチャットによる動員。いずれも合法スレスレです。これを防ぐには、行政や選管の対応を待つだけでは不十分です。市民側が「監視者」として機能する必要があります。
たとえば、選挙期間中に特定候補の誹謗中傷動画やデマ投稿を見かけたら、スクリーンショットを取り、自治体選管または総務省の「選挙違反通報フォーム」に送る。匿名でも構いません。通報が一定数を超えると、プラットフォーム側が削除・凍結を検討するケースもあります。報道機関やファクトチェック団体に連絡するのも有効です。
つまり、市民が選挙の免疫細胞として動くということです。
政治的中立を守りながら「民主主義の治安維持」を
参政党を批判すると「言論弾圧だ」「多様性の否定だ」と反論されることがあります。しかし民主主義とは、自由にデマを広げてよい制度ではありません。自由とは、真実を探す努力を前提に成り立つ秩序です。理性なき自由は暴走です。あなたの沈黙が、嘘を許容する社会を育ててしまう。だからこそ、個人が理性的な防衛者になる必要があるのです。
新聞を読む、事実確認をする、会話する、投票する。これらは小さな行動ですが、積み重なれば「感情による民主主義の乗っ取り」を防ぐ社会的ワクチンになります。あなたが一人でも、それを始めれば、参政党の感情ハック政治は計算通りには進まなくなります。
参政党の主張・政策を検証する
参政党が掲げる理念や政策を整理してみました。
次に、それが「日本に利するものかどうか」を批判的に考察します。つまり、選挙運動方法として問題視される点がある一方で、政策実現性・社会的影響・裏にある価値観から慎重に見るべき部分もあります。
主張・政策の内容
参政党は「教育・少子化・子育て支援」「食と健康・環境保全」「経済・財政・金融」「国防・外交」「エネルギー・インフラ整備」「国の仕組み・立法/行政/司法」「國體・国柄・国家アイデンティティ」の7分野を掲げています。
例えば、教育・子育て支援では「子ども一人ひとりへの経済支援」「教育関連給付金(0〜15歳へ月10万円)」という提案をしています。 また、国防・外交の分野では「日本の舵取りに外国勢力が関与できない体制づくり」などを重点として掲げています。
これらを一言で言うと、「停滞しつつある日本を再活性化させ、国柄・伝統を重んじながら変化を受け入れよう」というメッセージです。特に少子化・高齢化・デジタル化・グローバル化など、現在直面している構造的課題を国民の参加で乗り越えるというスタンスを取っています。
日本に利する面・実現可能性のある面
このテーマを「利するか」という視点で見たとき、まずポジティブに評価できるポイントがあります。
例えば、子育て支援・教育支援といった分野は日本社会が直面している重要な課題です。出産率の低下、教育格差の拡大、地域の活力低下など。参政党がこのような課題先進国としての日本を旗印にしているのは、少なくとも言及すべき点です。
また、国防・外交・国家アイデンティティを重視する姿勢も、日本が国際変化の中で自立した立場を取りたいという観点からは理解可能です。既存政党が“既得の枠組”に縛られて改革が遅れてきたという批判もあり、その意味で「変えよう」というメッセージは一定の魅力を持ちます。
しかし慎重に見るべき点・政策実現性・価値観の裏側
一方で、参政党の主張や政策には、少なくとも次の点で慎重な検討が必要です。
まず、教育給付金「0〜15歳へ月10万円」という提案。これは衝撃的で強いメッセージである反面、財源・制度設計・対象範囲の明確さに疑問が残ります。政策を掲げること自体は良いですが、実現可能性や副作用(例えば財政負担、インフレの懸念、既存制度との整合性)が検証されているわけではありません。
次に、国家アイデンティティ・「日本人の特徴や強みを活かす」という文言が、同時に「排外主義」や「閉鎖的な価値観」に転じやすいというリスクがあります。例えば「日本国籍を有する方を優先」という記述も一部に見られます。国家理念を掲げることは構わないのですが、それが民主主義・多様性・人権という観点で歪まないか、問い続ける必要があります。
さらに、運動手法・発信力・選挙戦略において、感情動員・ネット拡散という手法を積極的に用いていることが、政策議論よりも強調されているという批判もあります。つまり、政策自体は悪とは言えませんが、その実行・運動方法・背景にある動員構造に民主主義的健全さが伴っているかは別問題です。
まとめると、参政党の掲げる政策には確かに日本の構造的な課題を捉えたものがあり、理論的には「変革勢力」として魅力を持つ可能性があります。しかし、政策実現性・制度との整合性・価値観の幅(包摂性/多様性)・運動手法(情報戦略/動員)という観点から、当選しても問題ないかという判断には、慎重な検討が必須です。
政治は奪われるものではなく、守るもの
私たちは「情報の洪水」によって判断を奪われる時代に生きています。参政党はその構造を最も理解し、利用している政党です。
しかし、アルゴリズムは人間の理性を完全に凌駕できません。主婦の一言、会社員の一票、高齢者の疑問、それらの積み重ねこそが、社会を守る最大の防壁です。
あきらめないこと。それが最大の政治行為です。投票所へ行き、隣人と話し、真実を確認し続ける。民主主義は、あなたが今日も沈黙しなかった瞬間にだけ、生き残ります。


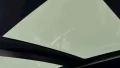
コメント