ついに日経平均株価が5万円の大台を突破しました。
米国のCPIが予想を下回り、米株が上昇した流れを受けての強い動きですが、「これはバブルなのか?」「もう買えないのか?」と感じる投資家も多いはずです。
PERとは?超シンプルに言うと「株価の人気度」
PER(株価収益率)とは、「株価が利益の何倍で取引されているか」を示す指標です。具体的には以下の計算式で求められます。
PERの計算式: 株価 ÷ 1株当たり利益(EPS)
たとえば1株の利益(EPS)が100円の企業の株価が1,000円なら、PERは10倍となります。これは「その会社の利益の10年分を払って株を買っている」という感覚です。
- PERが高い → 人気・成長期待が高い(グロース株)
- PERが低い → 割安・安定志向(バリュー株)
つまり、PERは「株がどれくらい人気なのか(期待されているのか)」を数値で表す指標なのです。
EPSとは?「企業の稼ぐ力」を表す数字
EPS(Earnings Per Share)=1株当たりの利益です。会社の儲けを株主1人あたりに換算した数字で、会社の実力を表す「体力測定」のようなものです。
EPSの計算式: 当期純利益 ÷ 発行済株式数
EPSが上がれば「利益を増やしている=企業価値が上がっている」ことを意味します。株価は基本的に「EPS × PER」で構成されるため、EPSが伸びれば株価も自然と上昇します。
日経平均の現状:PER25倍超は高すぎ?
2025年10月27日時点で、日経平均の予想PERは以下の通りです。
| 種類 | 予想PER | コメント |
|---|---|---|
| 指数ベース | 25.66倍 | かなりの高水準。米ナスダック級。 |
| 加重平均ベース | 19.28倍 | こちらも平時を上回る。 |
つまり、株価上昇は企業の利益(EPS)が増えたからではなく、「PER=期待の拡大」だけで押し上げられた状態です。やや息切れの危うさも見えます。
ただし「割高=危険」とは限らない理由
一見、PER25倍というのは割高に思えます。しかし、来期(2026年度)の企業業績が回復する見込みが強く、EPSが増加すれば「今の株価水準の正当性」が出てきます。
たとえば、現在のEPSが1,970円ですが、来期10%成長して2,167円になった場合を考えます。
| 株価(日経平均) | EPS | PER |
|---|---|---|
| 50,000円 | 1,970円 | 25.6倍 |
| 50,000円 | 2,167円(+10%) | 23.0倍 |
このように、企業が利益を増やせばPERは自然に下がり、株価の割高感も解消されます。つまり、いまは「利益の先取り相場」と見るのが正確です。
PER過熱局面で「絶対にやってはいけない」投資行動
- PERだけを見て高値追いをする(人気投票の延長で危険)
- 決算を無視してノリで買う
- グロース株に一極集中する(金利上昇時に下落しやすい)
- EPSが横ばいの企業を長期保有する
- 「市場平均が高いから安心」と思い込む(業種ごとに適正PERは違う)
逆にいま注目すべき「EPS成長セクター」
今後は「PER頼みの上昇」から、「EPS(利益)で評価される相場」に移行する可能性が高いです。
つまり、本当に稼げる企業が報われる相場です。
| セクター | 理由 | 代表的企業例 |
|---|---|---|
| 半導体製造装置 | 世界シェアが高く、設備投資再開で増益期待 | 東京エレクトロン、ディスコ、SCREEN HD |
| 電力・エネルギー | 再エネ・原発再稼働で安定収益 | 関西電力、中部電力、三菱重工 |
| 自動化・FA | 人手不足を背景に設備投資が拡大 | キーエンス、SMC、ファナック |
| 防衛・宇宙 | 政策支援と実需増加 | IHI、川崎重工 |
| 金融 | 金利上昇の恩恵でEPS改善 | 三菱UFJ、MS&AD |
PERの高さに怯えるより、EPSの伸びを見る
いまの日経平均は確かにPER25倍超えの高水準ですが、来期の企業利益回復を織り込んでいるとも言えます。短期的には調整リスクがある一方で、EPSを着実に伸ばす企業は引き続き評価されるでしょう。
つまり、投資家が見るべきは「PERの高さ」ではなく、利益が伸び続けるかというEPSのトレンドです。これが日本株投資で勝ち残るための、最もシンプルで確実な判断軸です。
いろんな指標を一つずつ知ることが大事
PERやEPSは最初は難しそうに見えますが、株式投資の「心臓部分」です。PERは人気、EPSは実力。どちらか一方に偏ると、相場の本質を見誤ります。
数字の裏にある「企業のストーリー」を理解できるようになれば、投資はぐっと面白く、そして安全になります。
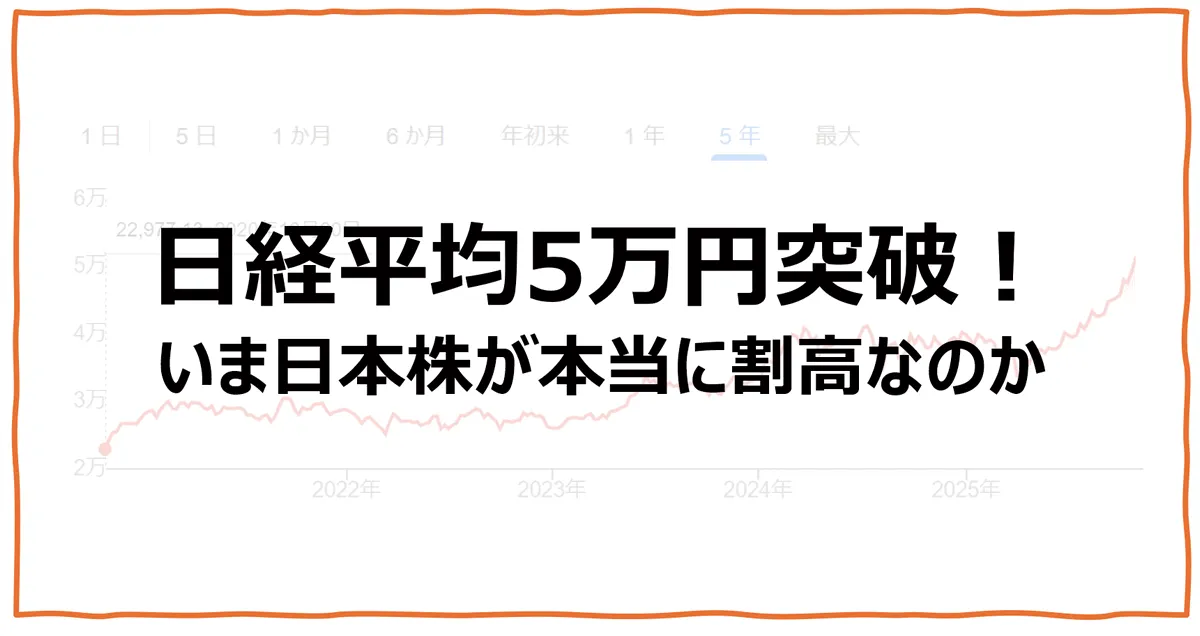


コメント