以下のミランの論文が話題です。原文は英語です。
ここで注目すべきは、ドルの過大評価を是正するための通貨政策。これらは実行されればドルの大幅な下落につながる可能性がありますが、論文の立場はあくまで「オプションの提示」であり、本筋の推奨ではない点に注意が必要です。
また、2025年に入って以降、アメリカは貿易政策の強化を明確に打ち出してきました。
しかし「何が既に実施され、何がまだ実施されていないか」を分けずに語ると、誤った行動(たとえば慌てて買い込むなど)を招きます。実際にアメリカがすでに実施している政策と、論文や議論で提起されているが未だ実行に至っていない為替・制度的施策を明確に分けたうえで、個人レベルで取るべき現実的な行動を整理します。
論文が指摘する課題
- ドルが基軸通貨として過剰に需要され、常に過大評価されている。
- 米国製造業は競争力を失い、赤字拡大が構造的に続いている。
- この不均衡を是正しなければ、米国の産業基盤と安全保障に悪影響が及ぶ。
論文で提案された通貨政策オプション
1. 多国間の通貨調整
他国に通貨の過小評価を是正させる外交的アプローチ。米国が協調的にドルを弱める方向を模索するものです。
2. 単独でのドル切り下げ(IEEPA活用)
国際緊急経済権限法を用いて米国が一方的にドル安誘導を行う可能性が提示されています。極めて強力で市場に衝撃を与えかねません。
3. 外貨準備の積み上げ
米国政府がドルを売り、外貨を買い入れることで、実質的にドルを弱める政策。為替市場に対する恒常的な圧力となり得ます。
4. 「強いドル政策」からの転換
長年の公式方針を改め、弱いドルを産業回復の手段とする発想が論文内で検討されています。
重要な点: これらはいずれも「実際にやるべき施策」と断言されているのではなく、「選択肢(オプション)」として整理されています。つまり、必ず実行されるわけではありません。
ドル暴落につながるシナリオ
- 米国が公式にドル安政策を採用し、大規模介入を実行。
- 他国が一斉に準備通貨をドルから分散。
- 米国債への信認が揺らぎ、海外投資家が保有を減らす。
こうした条件が重なればドルの暴落リスクは高まります。ただし2025年時点では、これらが揃ってはいません。
日本人が個人でできる備え
- 資産分散: 円・ドルに偏らず、ユーロや金なども組み込む。
- 消費判断: 為替リスクが直撃する輸入依存品(燃料・食料・家電など)をリスト化し、必要に応じ優先購入を検討。
- 情報収集: 米財務省の為替報告や国際金融ニュースを定期的にチェック。
- スキル・収入源の多様化: 為替や国際貿易に左右されにくい分野に強みを持つ。
Hudson Bay Capital の論文は「ドル暴落」を直接推奨しているわけではありません。
しかし、ドルを弱める方向の政策オプションを具体的に列挙しており、実行されればドル安・暴落につながり得ます。個人としては過度に悲観するのではなく、「オプションがある=可能性がゼロではない」と理解し、冷静に分散や備えを進めることが重要です。
以下ではドル暴落を煽っていますが、注意が必要です。
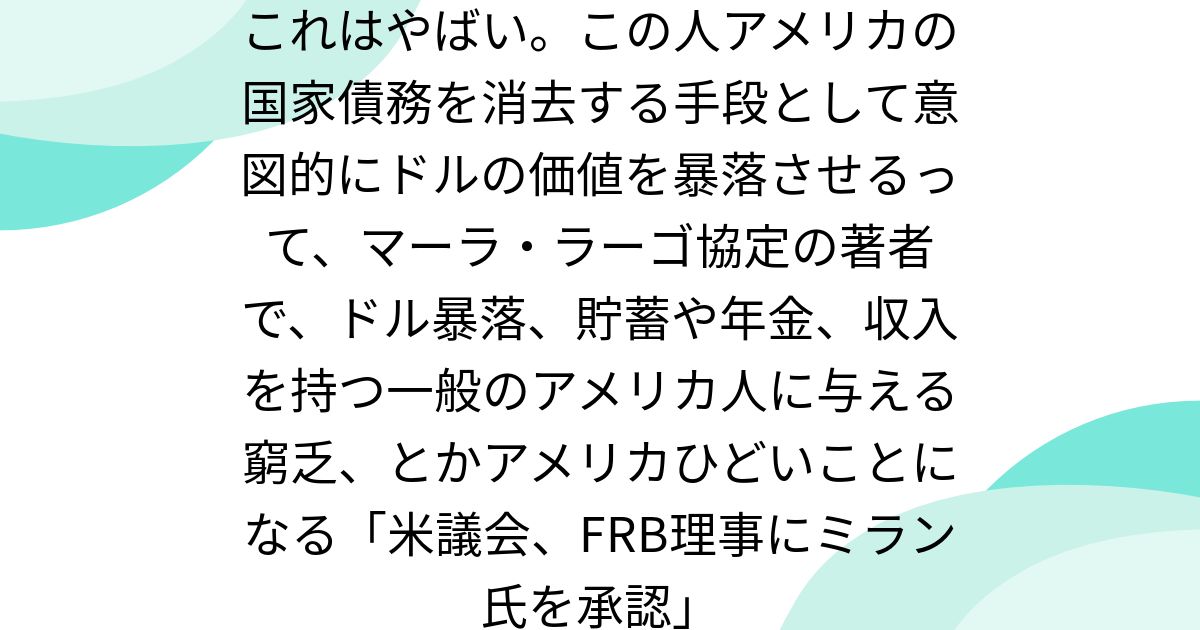
次に、実施済み、未実施の施策をみていきます。
前提:なぜ「実施済み/未実施」を分けるのか
政策の実施可否は経済への影響の即効性を左右します。
実施済みの施策は既に市場に織り込まれつつあり、短中期で影響が出やすいです。
一方、為替面の大きな制度変更や公的介入は政治的・国際的制約が大きく、宣言だけで終わることも多いです。したがって、両者を混同すると「いま買うべき」「いま売るべき」の判断を誤ります。
第1部:アメリカがすでに実施した施策(2025年時点)
1. 関税強化(相互主義関税の導入)
2025年に相互主義的な追加関税の導入が発表され、対象国・対象品目に対する関税率引き上げが実行されています。米国は交渉カードとして関税を使い、譲歩がなければ高関税を維持する方針です。結果として輸入品の価格付けに影響が出始めています。
2. 特定品目への高率関税(鉄鋼・アルミ等)
鉄鋼・アルミを中心に25%〜50%の関税が課されています。これにより該当素材を使う産業(自動車・建設・機械など)は原材料コスト上昇の影響を受けやすくなっています。
3. 自動車・部品への追加関税
自動車及び自動車部品への高関税措置が取られており、完成車輸入や海外生産のサプライチェーン見直しを促しています。これらは製造移転や価格に短期〜中期の影響を与えます。
4. 非関税措置と貿易制裁的な運用
エネルギーや安全保障を理由とした二次的な貿易制裁(例:特定国からの石油の取り扱いを巡る制裁の波及)等が実際に運用されています。貿易と安全保障を連動させる実務が進行しています。
豆知識: 関税は「保護」だけでなく「交渉手段」です。相手国が譲歩すれば関税を緩めることができるため、関税は必ずしも永久的な価格上昇を意味しません。ただし交渉が長引けば価格は高止まりします。
第2部:論文や議論で提起されているが未実施/限定的にしか実行されていない施策
1. 公的な為替操作(大規模な相場介入や通貨切り下げの公式運用)
理論的には「為替を意図的に操作して輸出競争力を回復する」ことが議論されていますが、2025年時点で米国が公に大規模な為替操作(たとえば自国主導でドルを意図的に切り下げる政策)を実行したという事実は確認できません。為替については監視や報告(財務省の為替報告書など)が行われていますが、強制的な罰則付き為替政策や恒常的な市場介入は限定的です。
2. 国際制度の再編(新たな多国間通貨体制や準備通貨代替の実装)
論文では「ドル中心体制の見直し」や「代替的リザーブ通貨の採用」が提案されていますが、これらは制度設計・多国間合意が必要なため短期で実施されていません。実務としてはまだ話し合い・報告フェーズに留まっています。
3. 為替に対する罰則的関税や自動トリガー制度の実装
為替操作と関税を自動連動させるような厳格な制度設計も提案されていますが、国際法やWTO的制約、相手国との報復リスクを勘案して実装されていません。要するに「為替で相手を直接叩く」ような制度は未整備です。
豆知識: 為替は金融市場で24時間動くため、政府が恒常的に「望む方向」に動かすことは政治的コストと市場の反発が大きいです。そのため為替政策は「監視」と「圧力」に留まることが多いです。
第3部:実施済み施策が意味することと、未実施の為替施策が不在であることの実務的含意
市場への織り込みとタイムライン
関税強化は既に実行段階にあるため、素材コストや一部輸入製品の価格には短期〜中期に反映されます。一方で為替に関する制度的措置が不在であるため、為替相場自体は「市場の需給・金利差・資本フロー」により決定され続けます。つまり、輸入品価格が上がるかどうかは「関税」「物流」「為替」の複合要因で決まるため、単純に“今すぐ買え”とは言えない状況です。
誤解しやすい点(購買行動の見直しに関する注意)
「関税が上がった → 今すぐ輸入品を買い溜めすべき」という結論は短絡的です。理由は以下の通りです。
- 関税が実際に価格転嫁されるかは小売業者や流通の在庫、為替の動き次第であること。
- 一時的な在庫やセールの存在で、むしろ待った方が安く買えるケースがあること。
- 長期的にはサプライチェーンの再編で品質・価格の見直しが起き、即断が裏目に出る可能性があること。
第4部:個人が取るべき現実的で安全なアクション(為替施策未整備を踏まえた改訂版)
A. 「即買い」ではなく「優先順位と分散」で動く
生活必需品や消耗品の即時買い溜めはコストや保管の負担が増えるだけで逆効果になることがあります。
まずは輸入依存度が高く、価格変動が生活に直結する品目をリスト化し、優先順位をつけて対応します。高影響度(例:特定薬、特定の食品、燃料関連)については短期的備蓄を検討し、家電やガジェットはセールや価格情報を比較して判断します。
B. 資産防衛は「通貨分散」と「ヘッジの選択」
為替介入が十分でない現状では、為替変動の被害を完全に防げません。したがって、以下を推奨します。
- 円資産と外貨資産のバランスを保つ(ドルだけでなくユーロや金などの分散も検討)。
- 投資商品を選ぶ際は為替ヘッジ有無を意識する。為替ヘッジ型ETFやヘッジなしETFの違いを理解する。
- 海外旅行や留学、海外送金が予定されている場合は早めにレートと手数料を比較して決済タイミングを最適化する。
C. 消費を「賢く待つ」判断基準を持つ
購入を急ぐべきか待つべきかの簡単な判断ルールを作ると有効です。例:
- 必需品で「代替がない」→ 優先的に確保。
- 耐久消費財で「長期セール予定が明確」→ セールを待つ。
- 高額商品の場合、為替・関税のニュースを短期的に追い、値動きの方向性が明確なら購入判断を行う。
D. スキル・収入源の多様化を急ぐ
関税や貿易摩擦は産業構造の変化を促します。個人としては付加価値の高いスキル(データ解析、サプライチェーン管理、貿易実務、言語力、ITスキル等)を強化し、複数の収入源を持つことがリスクヘッジになります。
E. 情報ソースを整理する
追うべきソースの例は以下です。
- 米財務省の為替報告(Exchange Rate Reports)
- 米国政府の通商関連発表(関税・制裁の告示)
- 信頼できる経済メディア(日本経済新聞、Financial Times、Reutersなど)
豆知識: 「今すぐ買う」意思決定をする前に、3つのチェックを習慣化しましょう。1) 代替可能か。2) 保管・維持コストは許容範囲か。3) 価格が下がる可能性が高くないか。これで衝動買いの被害を減らせます。
実施済み施策には備え、未実施(為替)には過度に期待しない
ポイントを整理します。アメリカは関税強化という「実施済みの武器」を使っているため、輸入品や素材コストへの短中期の影響は現実にあります。
一方で、為替面での制度的な介入・操作は限定的であり、そこに過剰な期待を寄せることは危険です。したがって、個人レベルでは「何を即時に備えるべきか」を優先順位で判断し、資産は通貨分散とヘッジで守り、スキルと情報で長期的に備えることが最も現実的で強固な対策になります。
これらの対策は大仰な政治介入を期待せずとも、個人の生活と資産を守れる実効的な手段です。ぜひ今日からリスト化と優先順位付けを始めてください。



コメント